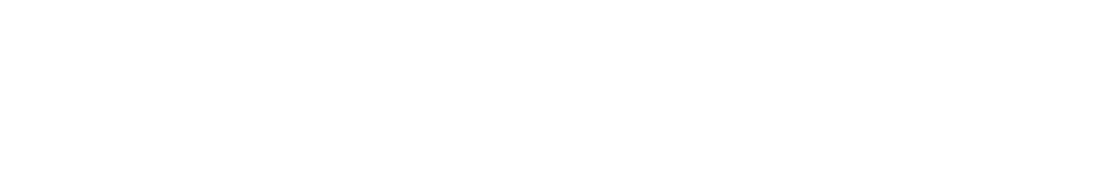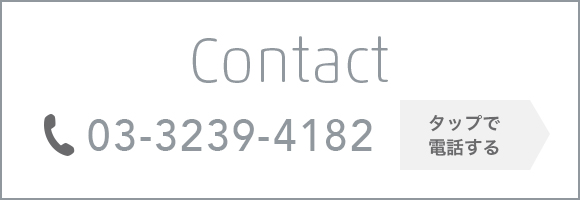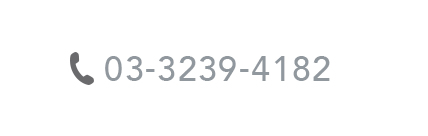歯周病とは
 口の中が健康か否かにかかわらず、誰の口の中にも歯周病菌がいます。そしてこれらが集まると歯垢という物質になります。毎日歯磨きしても歯垢を完璧に落としきることはできないため、少しずつ歯と歯肉の間などに溜まっていきます。やがて歯周病菌は歯垢の中で毒素を出しはじめ、それにより歯肉の炎症・腫れ・出血が見られるようになります。
口の中が健康か否かにかかわらず、誰の口の中にも歯周病菌がいます。そしてこれらが集まると歯垢という物質になります。毎日歯磨きしても歯垢を完璧に落としきることはできないため、少しずつ歯と歯肉の間などに溜まっていきます。やがて歯周病菌は歯垢の中で毒素を出しはじめ、それにより歯肉の炎症・腫れ・出血が見られるようになります。
それだけでなく、目に見えない歯槽骨(歯を支える骨)も少しずつ溶けはじめるので、やがて歯がグラつくようになります。そして、放置していると最終的には歯が抜け落ちてしまいます。これを『歯周病』といいます。中高年以上の年齢の方がなる病気と思われている方が多いようですが、
年齢に関係なくお子さまや若い方もなる病気です。そして、日本人の成人の80%以上の方に発症しているといわれる、国民病ともいうべき病気です。
虫歯とは異なり、歯周病になっても痛みなどは特に感じないので、自覚症状のないまま進行します。そのため、異変に気づいたときには重症になっているということも珍しくありません。しかし、いくら気づきにくい病気とはいえ、進行の途中で必ず口の中に異変が現れてくるものです。
軽症であれば通院の回数や治療費が負担にならずにすむので、早い段階で歯周病に気づけるよう、進行のしかたと症状を知っておきましょう。もちろん、毎日正しい歯磨きをして、意識的に予防することも大切です。

 歯周病の進行
歯周病の進行
『歯周病』は、歯周組織(※)に炎症が起こる病気の総称です。最初に歯肉に炎症が起き、少しずつ範囲が広がって最終的に歯槽骨(歯を支える骨)まで炎症が及ぶなど、歯周組織全体が破壊されてしまいます。各段階で、主に以下のような症状がみられます。
※歯肉、歯槽骨(歯を支える骨)、セメント質(歯根の表面を覆う組織)、歯根膜(歯根と歯槽骨を繋ぐ組織)
-
歯肉炎
歯周ポケットは2〜3mmほどになります。歯肉に炎症が起きている状態で、歯を磨くときに出血しやすくなります。

-
歯周炎(軽度)
歯周ポケットは4〜5mmほどになります。歯肉の炎症がひどくなり、歯槽骨や歯根膜も破壊されはじめている状態です。歯肉の腫れや出血だけでなく、口臭を感じたり冷たい水がしみます。

-
歯周炎(中等度)
歯周ポケットは6〜7mmにもなります。歯槽骨が半分ほど破壊された状態で、指で歯を押すとグラつきます。歯肉の腫れや出血だけでなく、歯が浮くような感じがしたり、口臭が悪化します。

-
歯周炎(重度)
歯周ポケットは8mmほどと非常に深くなります。歯槽骨が2/3以上破壊された状態で、歯がグラグラになります。歯肉が下がって歯根が露出するので、歯が長く見えたり、歯肉から膿が出て口臭がより悪化します。この状態を放置すると、最終的に歯が抜け落ちてしまいます。

歯周病の治療方法
 歯周病は初期状態においては、正しい方法で歯磨きをすることで進行を抑えることが可能です。ですが、もし歯周病が悪化してしまった場合には、以下のような方法で治療をすることができます。
歯周病は初期状態においては、正しい方法で歯磨きをすることで進行を抑えることが可能です。ですが、もし歯周病が悪化してしまった場合には、以下のような方法で治療をすることができます。
スケーリング
スケーラーという専用器具を使って歯垢や歯石を取り除く処置です。軽度の歯周病であれば、スケーリングを行なって正しい歯磨きを続けることで、治る可能性があります。
ルートプレーニング
スケーリングを行なった後に、歯垢や歯石の歯の再付着を防ぐ処置です。スケーリング後のザラザラになった歯の表面をツルツルにします。中等度の歯周病の場合に行ないます。
フラップ手術
歯肉を切開して歯周ポケットの奥深くの歯石を取る外科処置です。歯肉に覆われた歯根の部分の歯石を取り除きます。重度の歯周病になっている場合に行ないます。
GTR法
歯肉を切開して歯周ポケットの奥深くの歯石を取り、歯肉と歯槽骨の間に人工膜を入れて、組織の再生を促す外科処置です。人工膜には、再生させる部分が歯肉で覆われるのを防ぐ働きがあります。
エムドゲイン法
『エムドゲイン』というたんぱく質の一種を主成分としたゲルを注入し、組織の再生を促す方法です。エムドゲインは豚の歯の芽から抽出したもので、再生させる部分が歯肉で覆われるのを防ぐ働きがあります。